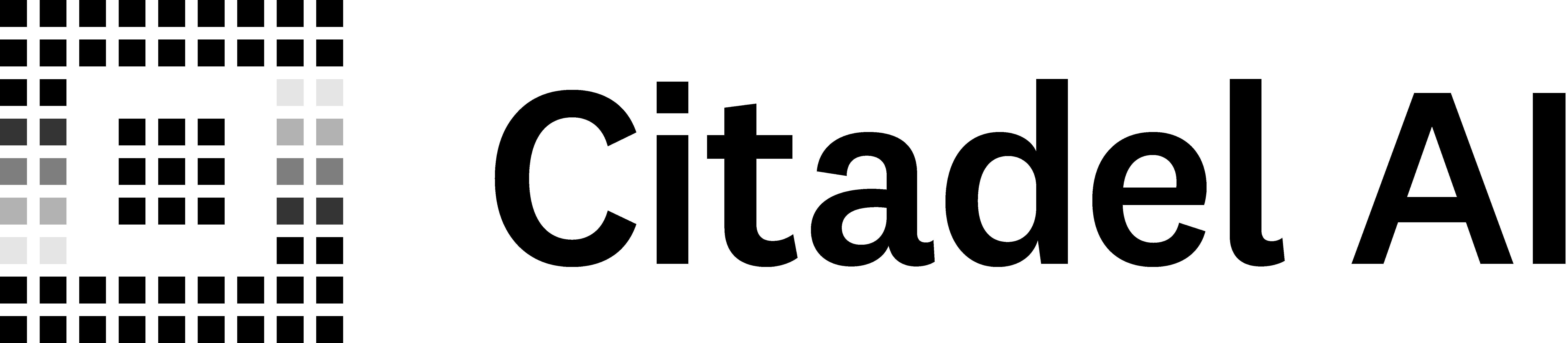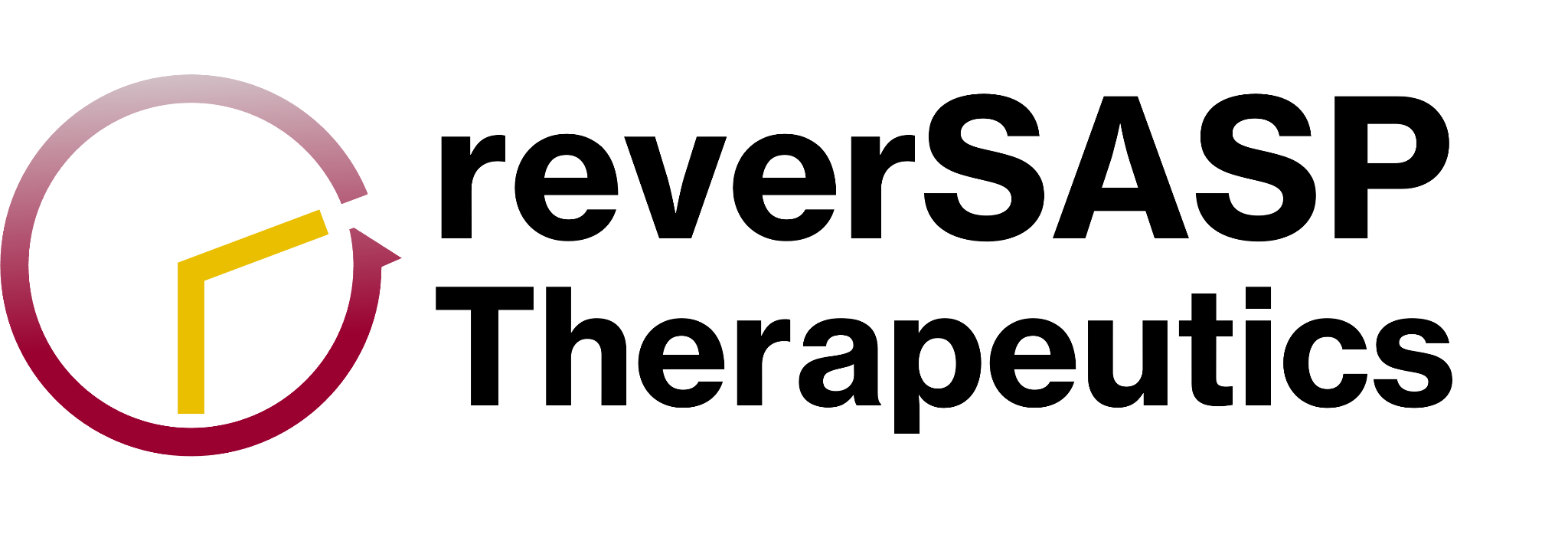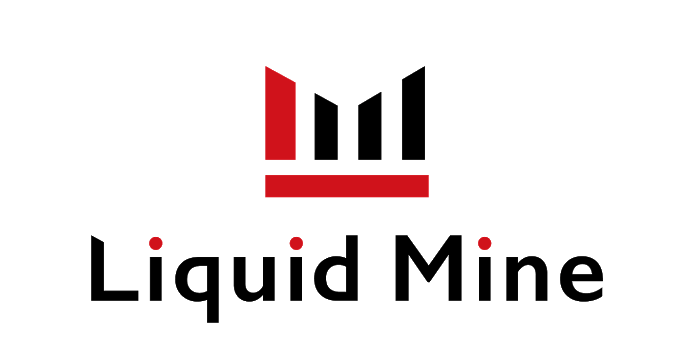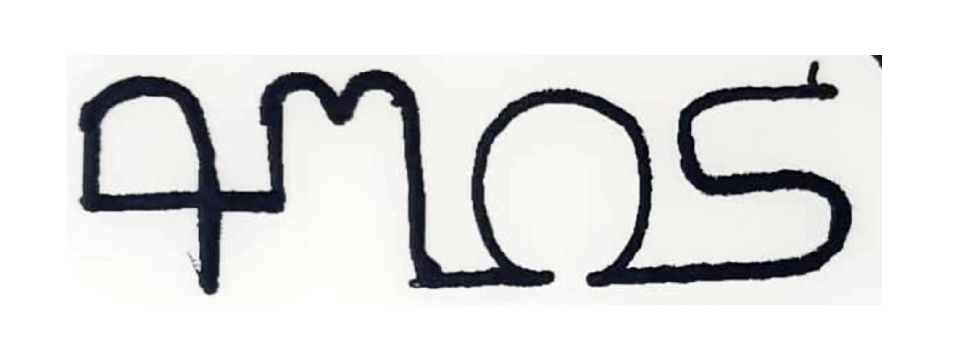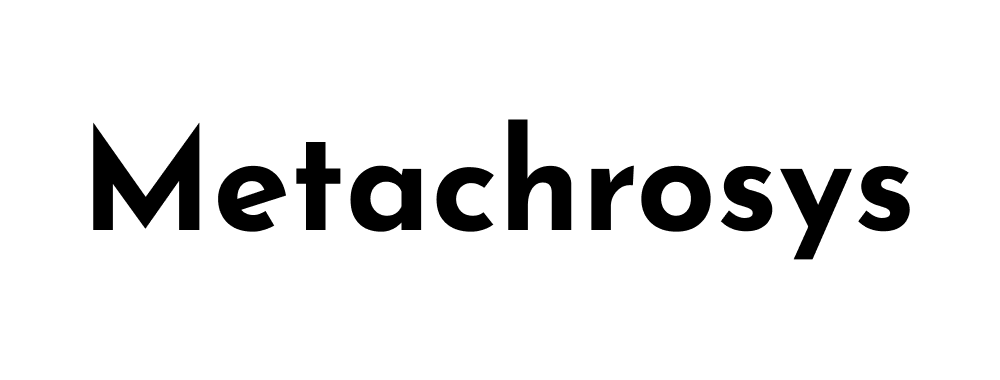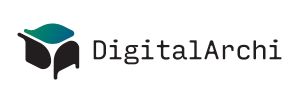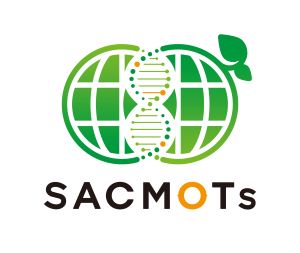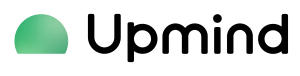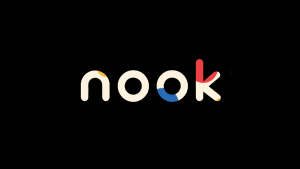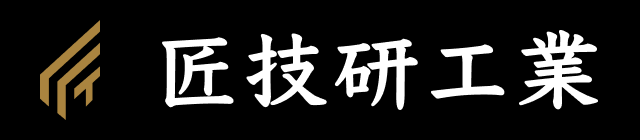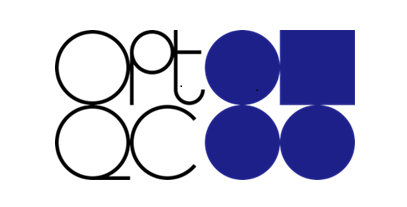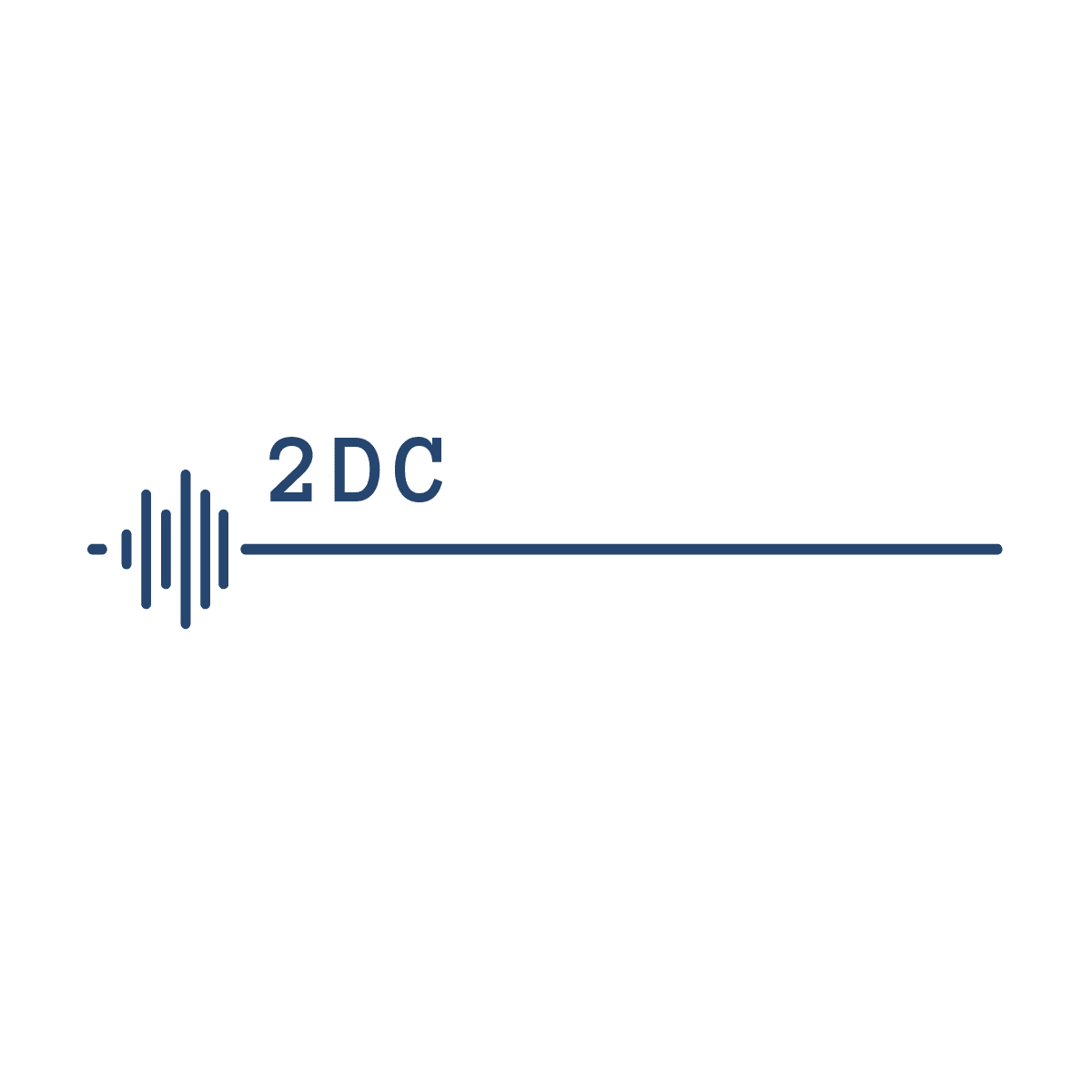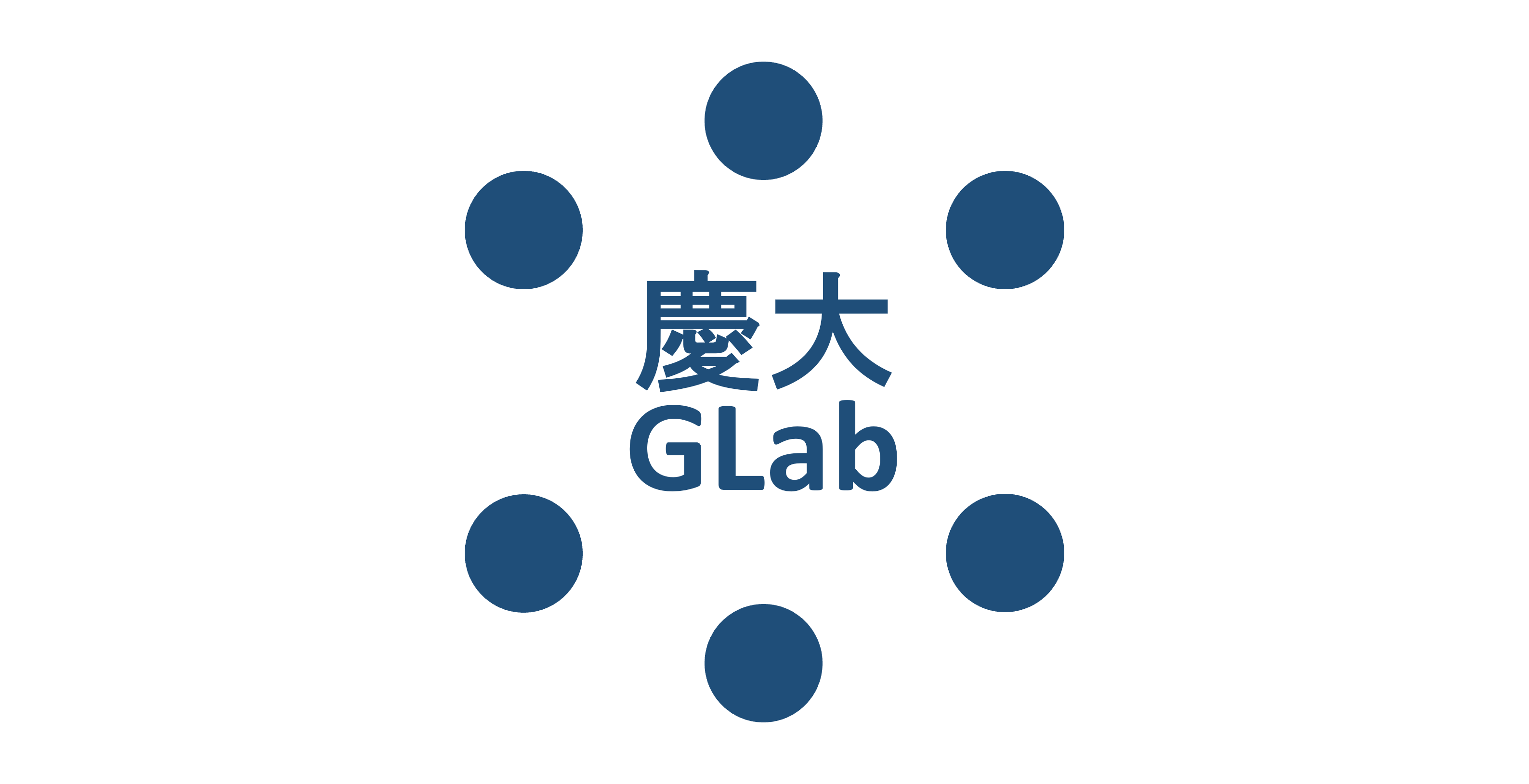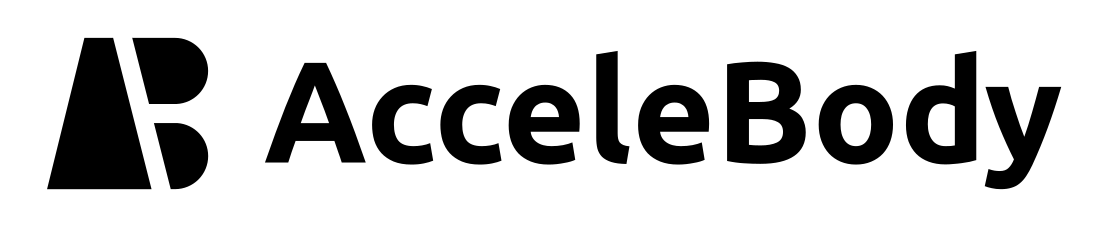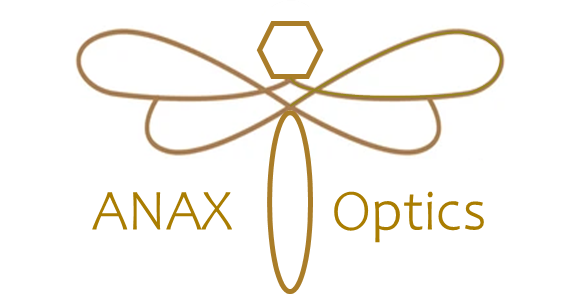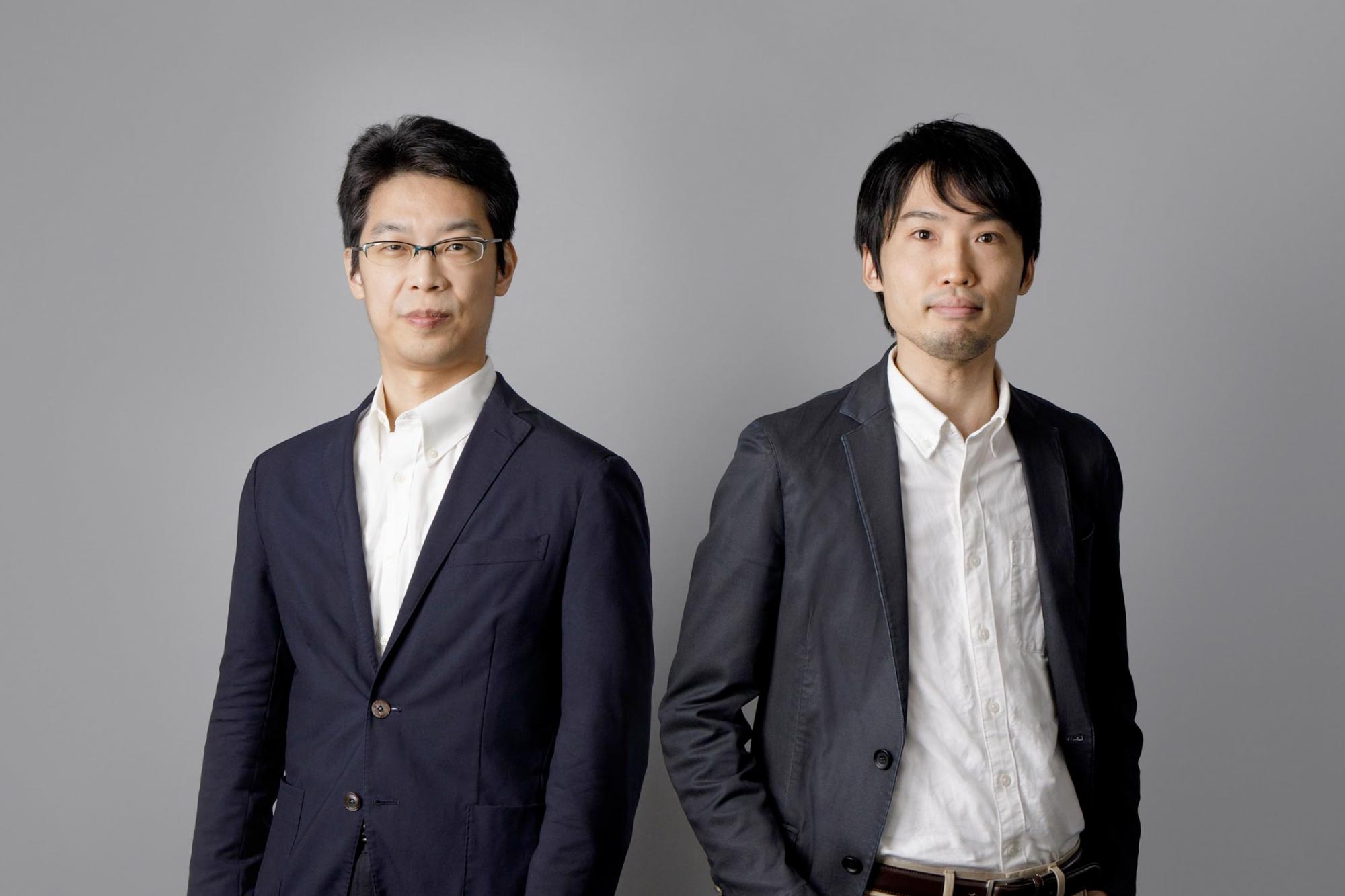「1stRound」は、アカデミアに関連する優れた技術や着想の事業化、社会実装を支援する国内最大のアカデミア横断型インキュベーションプラットフォームです。アカデミアにおける技術シーズは多数ある一方で、早期事業化における支援サポートはまだ十分ではないのが現状です。「1stRound」では、初動を加速させるための資金支援をはじめ、経営人材の育成・発掘、事業連携等のネットワークを共有することでアカデミアの垣根を超えたベンチャー創出および育成を目指しています。
技術シーズの社会実装を支援、国内初、大学横断・Non-Equity型最大規模の起業支援プログラム
※1 2021年4月に、東京大学に加え、筑波大学、東京科学大学(24年10月東京医科歯科大学、東京工業大学が統合) が参画し国内初の大学共催起業支援プログラムへと進化しました。
2022年4月、神戸大学、名古屋大学、一橋大学、北海道大学
2023年3月、九州大学、慶應義塾大学、立命館大学、立命館アジア太平洋大学、早稲田大学
2024年4月、沖縄科学技術大学院大学学園(OIST)、金沢大学、近畿大学、東京理科大学、日本原子力研究開発機構(JAEA)、量子科学技術研究開発機構(QST)
2024年10月、静岡県立大学、奈良先端科学技術大学院大学(NAIST)、理化学研究所、宇宙航空研究開発機構(JAXA)
以上、18大学4国立研究機関が参画しています。
過去採択企業の資金調達成功率は約90%以上、大手企業との協業も拡大
また、関連大学の起業家教育プログラムとの連携により、全採択数のうち再応募からの採択は20~25%を占めており、アカデミアからの起業をより後押しする、エコシステム構築を目指しています。
新たに味の素、ENEOS Xplora、関西電力が参画し総勢24社へ
※2 JR 東日本スタートアップ株式会社、ピー・シー・エー株式会社、芙蓉総合リース株式会社、三井住友海上火災保険株式会社、三井不動産株式会社、三菱重工業株式会社、BIPROGY株式会社、東日本高速道路株式会社、日本ゼオン株式会社、エプソンクロスインベストメント株式会社、三菱地所株式会社、Yamauchi No.10 Family Office、ダイキン工業株式会社、株式会社STNet、三井物産株式会社、ホンダ・イノベーションズ株式会社、日立建機株式会社、三菱商事株式会社、阪急阪神ホールディングス株式会社、九州電力株式会社、株式会社サニックス(順不同)
第12回「1stRound」採択企業
- 株式会社DubGuild
代表取締役CEO 大嶽匡俊
DubGuildは「世界で最も優れたAI吹き替え技術」を開発し、あらゆるコンテンツが世界中へ届けられる未来を切り拓くことを目指しています。弊社の製品では、原作の魅力を引き出しながら、吹き替え先言語の話者が求める幅広い表現を生み出すためのAI吹き替え技術や、それを活用するインターフェースを提供しています。CS専攻を中心とした音声・自然言語処理を専門とする研究者が集まり、研究開発に取り組んでいます。ぜひ私たちの仲間に加わってください!
- AcceleBody株式会社
代表取締役CTO 青木治雄、代表取締役CEO 中村 綾太
私たちは、人生最後の10年の健康を脅かす足腰の問題に挑んでいます。整形外科でのリハビリテーションでは、品質(評価や治療の質)と量(患者数や収益)の両立が難しいという課題があります。そこで私たちは、ロボット制御技術を応用することで、1台のカメラで、これまで臨床現場では難しかった関節負荷などの治療に役立つ指標を1分で信頼性高く計測できる動作分析システムを開発しています。この技術を全国1.7万件の整形外科へ提供し、人々の健康寿命の延伸に貢献することを目指します。
- 株式会社QioN
代表取締役社長 CEO 平野祥久
私たちは、肥料やクリーン燃料といった人類の生活を支える物質の原料であるアンモニアを、どこでも、低コストで製造する技術の開発に挑戦しています。この課題を解決するため、再生可能エネルギーを用いて身近な原料と電気から従来法を超えるエネルギー効率でアンモニアを得る手法を開発し、従来より小規模な製造でも半分以下のコストで製造できる製造技術の確立を目指しています。年間150万トン以上あるグローバルアンモニア需要の15%に提供することで、コストやCO2の削減、ひいては飢餓や紛争といった社会課題の解決を目指します。
- YasAI
代表 水谷航悠、平田裕也
私たちは農業界の人手不足問題を解決するため、農作物の等級を自動で判定するAI選果システム「YasAI」を開発してきました。 NEDO NEP開拓コース、未踏アドバンストを経て1stRoundに採択され、現在はAI技術の既存産業への応用を目指し、選果のほか様々な事業機会を探索中です。
- 株式会社Freezo
代表取締役CEO 水野竣介
私たちFreezoは、大型の冷凍冷蔵倉庫に対して、独自のAI・数理最適化技術により冷凍機を自動で最適に制御することで電気代を削減する制御システムを開発しています。将来的には、複数の冷凍機をまとめて制御することで調整力としての活用も目指しています。冷熱を活用してカーボンニュートラル社会の実現に貢献していきます。
- 株式会社fff fortississimo
代表取締役(CEO)入澤寿平
https://fff-fortississimo.com/company/
私たちfff社は世界最高レベルの技術を基盤とした、最先端繊維材料の開発とその事業化に挑戦しています。特に、省エネ・新エネ分野で欠かせない素材である炭素繊維の事業化に注力しています。その製造コストが用途拡大の障壁であった中で、特有の物性は既存品のまま、サステナブルな原料から低コストな製造方法を確立しています。未来型炭素繊維でこの業界に革新を起こしてまいります。
- ANAX Optics株式会社
CEO 桐野宙治
私たちANAX Opticsは革新的な光学設計技術をもとに起業し、光学設計や製造を支援するソフト開発で業界全体のパイを拡げ、人類社会へ貢献することを目指しています。独自技術で進化させたライトフィールド光学を用いて、工業検査カメラや三次元光ピンセットの開発も行い、新たなイノベーションの芽を育てます。
- SAKIYA株式会社
代表取締役 渡邉顕人・野田元 技術顧問 山口大翔
弊社は、電磁波を用いた透視スキャン技術により、木材の節・密度・強度を計測・可視化する技術を開発しています。数ミリ単位の欠点まで検出・可視化できるため、木取りなどの工夫による歩留まりの大幅な向上や、加工作業の手戻り削減に寄与します。木材は内部の状態が個体ごとに異なるうえ、非破壊検査技術がほとんど普及していなかったことから、歩留まりの向上や性能評価が難しい分野でした。弊社はこの課題に対して、木材の検査プロセスを抜本的に変革し、さらなる品質向上と安定供給に貢献してまいります。
- Hasana Biosciences Inc.
President and CEO William Kuziel
Hasana Biosciencesは、自己免疫疾患や炎症性疾患に対する新たな治療コンセプトを切り開く革新的なバイオテクノロジー・スタートアップです。Hasana Bioは、世界トップクラスのリーダーシップチームとバイオ医薬品の創薬・開発における専門知識を活かし、アトピー性疾患の治療に向けた新たなモダリティと革新的な医薬品に注力しています。
技術シーズの社会実装を支援、国内初、大学横断・Non-Equity型最大規模の起業支援プログラム
※1 2021年4月に、東京大学に加え、筑波大学、東京科学大学(24年10月東京医科歯科大学、東京工業大学が統合) が参画し国内初の大学共催起業支援プログラムへと進化しました。
2022年4月、神戸大学、名古屋大学、一橋大学、北海道大学
2023年3月、九州大学、慶應義塾大学、立命館大学、立命館アジア太平洋大学、早稲田大学
2024年4月、沖縄科学技術大学院大学学園(OIST)、金沢大学、近畿大学、東京理科大学、日本原子力研究開発機構(JAEA)、量子科学技術研究開発機構(QST)
2024年10月、静岡県立大学、奈良先端科学技術大学院大学(NAIST)、理化学研究所、宇宙航空研究開発機構(JAXA)
以上、18大学4国立研究機関が参画しています。
過去採択企業の資金調達成功率は約90%以上、大手企業との協業も拡大
また、関連大学の起業家教育プログラムとの連携により、全採択数のうち再応募からの採択は20~25%を占めており、アカデミアからの起業をより後押しする、エコシステム構築を目指しています。
新たにサニックスが参画し総勢23社へ
※2 JR 東日本スタートアップ株式会社、ピー・シー・エー株式会社、芙蓉総合リース株式会社、三井住友海上火災保険株式会社、三井不動産株式会社、三菱重工業株式会社、BIPROGY株式会社、東日本高速道路株式会社、日本ゼオン株式会社、エプソンクロスインベストメント株式会社、三菱地所株式会社、Yamauchi No.10 Family Office、ダイキン工業株式会社、株式会社STNet、三井物産株式会社、ホンダ・イノベーションズ株式会社、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社、日立建機株式会社、三菱商事株式会社、阪急阪神ホールディングス株式会社、九州電力株式会社、東邦ガス株式会社(順不同)
第11回「1stRound」採択企業
- OptQC株式会社
CEO 高瀬 寛
当社は「光」と「量子」が持つ高速情報処理の潜在能力を実用技術として具現化し、光量子コンピュータを基盤とした超スマート社会を実現します。当社は東京大学大学院工学系研究科の古澤・遠藤研究室からスピンアウトした、世界屈指の研究者集団です。2025年度中に光量子コンピュータを商用化し、独自のメンバーシップ制度を通じて利活用を促進します。
- 株式会社ディメンジョンフォー
代表取締役CEO 出川 章理
当社は名古屋大学未来材料・システム研究所長田研究室の研究成果をベースに、ポストグラフェン材料として注目される無機ナノシートを利用した薄膜技術、電子デバイスの開発を行います。インク1滴、1分で薄膜製造を実現する独自コーティング技術を高度化し、従来技術よりも圧倒的に安く、速く、高い特性を有する薄膜、電子デバイスの製造を実現します。
- RecycLi
代表取締役CEO CTO 佐々木 一哉
https://lrro.hirosaki-u.ac.jp/ (弘前大学リチウム資源総合研究機構HP)
RecycLiは、特定重要物資であるリチウム資源を安定供給する課題に対し、使用済み電池や塩湖かん水などから電池グレードを超える高純度リチウムを格段に低コストで抽出する技術・装置提供します。リチウムを含有する多様な溶液から、薬品を全く使用せず電力供給だけで抽出できる環境負荷が小さい技術です。低濃度溶液からの採取も可能です。 (設立準備中)
- 株式会社Jizai
代表取締役CEO 石川 佑樹
Jizaiは、急速な少子高齢化や労働力人口の減少などの課題に対して、AIソリューション/AI SaaS事業・AIロボット事業など生成AI・ロボット領域の社会実装を行います。また、マルチモーダルAIによる制御とタスクの遂行を可能にするハードウエアを研究・開発することで、汎用AIロボットの実現を目指します。
- Rebio Health
柿花 隆昭・岡本 章玄
物質・材料研究機構の岡本章玄が開発した革新的な電気化学殺菌技術を活用し、医療分野における難題に挑んでいます。特に、従来の手術や薬物治療では解決が難しい整形外科インプラント感染や創傷感染といった「バイオフィルム感染症」に対して、低侵襲かつ高い効果を発揮する医療機器の開発を進めています。この電気化学殺菌技術は、医療分野にとどまらず、食品安全や船底の汚染対策といった幅広い分野にも応用可能で、多岐にわたる課題解決への貢献を目指しています。(設立準備中)
- Paletter, Inc.
CEO 井上 正彦
当社は、採用担当者本人のテイストを持った分身AIによるスクリーニングサービスを提供します。これにより採用面談での『イメージのズレ』を減らし、面談回数の削減を実現します。創業者自身が抱えていた課題を元に日本でサービスを開発後、2023年にアメリカで起業。『すべての候補者と採用担当者がストレスなく完全最適される社会の実現』を目指します。
- 株式会社カルマリオン
代表取締役 吉竹純基 Co-founder 乾幸地
私達は、AI技術とシミュレーションを組み合わせて、土木事業や製造業において「少数の観測データから超高精度のデータ同化をおこなう」「欲しい性質から、作るべき構造を自動設計する」ことを可能にする技術ベンチャーです。Co-founderの乾が東京大学工学系研究科で開発していた逆解析技術を社会実装するために設立しました。この技術を使って、複雑な現実をデジタル化することで、大きなコスト削減と革新的な開発に貢献します。
- 株式会社アンチキャンサーテクノロジズ
CEO 西野 輝泰
膵がんは年間約4万人の方が罹患しますが、5年生存率は僅か9%であり、最も悪性のがんとされています。約8割の方は発見時には手術ができない状態であり、抗がん剤の効果も極めて限定的です。同社は膵がんに対する「光免疫療法」を開発中であり、基礎理論は既に完成しています(特許出願中)。この新しい治療法を一刻も早く患者様に届けることを目標にしています。
技術シーズの社会実装を支援、国内初、大学横断・Non-Equity型最大規模の起業支援プログラム
※1 国立大学法人東京大学、国立大学法人筑波大学、国立大学法人東京医科歯科大学、国立大学法人東京工業大学、国立大学法人神戸大学、国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学、国立大学法人一橋大学、国立大学法人北海道大学、国立大学法人九州大学、学校法人早稲田大学、学校法人慶應義塾、学校法人立命館(立命館大学/立命館アジア太平洋大学)、学校法人東京理科大学(2023年12月時点)
コーポレートパートナーとして新たに九州電力、東邦ガスが参画、総勢22社へ。
※2 株式会社STNet、NTTコミュニケーションズ株式会社、エプソンクロスインベストメント株式会社、JR東日本スタートアップ株式会社、ダイキン工業株式会社、日本ゼオン株式会社、阪急阪神ホールディングス株式会社、ピー・シー・エー株式会社、東日本高速道路株式会社、日立建機株式会社、BIPROGY株式会社、芙蓉総合リース株式会社、ホンダ・イノベーションズ株式会社、三井住友海上火災保険株式会社、三井不動産株式会社、三井物産株式会社、三菱商事株式会社、三菱地所株式会社、三菱重工業株式会社、Yamauchi-No.10 Family Office(五十音順)
第10回「1stRound」採択企業
- 株式会社MQue
代表取締役 津田 拓也
MQueは、航空宇宙発の高精度な流体 (単相流・二相流) シミュレーション、物理シミュレーションの高速化、3Dデザイン生成など、複数の世界トップレベルの技術を独自の強みとして、主に流体シミュレーションの開発を行っています。マックスプランク研究所、東大航空宇宙、NVIDIA、マッキンゼー等の経歴を持つ世界トップレベルのエンジニアとビジネスメンバーがチームとなり、製造業をはじめとするお客様の製品開発の品質・コストの課題を解決していきます。
- SACMOTs(サクモツ)
田島 大地・村上 真哉
「低農薬・低肥料で高収量・高付加価値の食料生産 」の実現を目指す、九州大学発のチームです。チームメンバーは、ビジネス・研究サイドともに研究室のOB・OGで構成され、100年以上の歴史がある作物学研究室の「植物の収量・品質向上」に関する圃場から実験室レベルでの知見を活かし事業展開を目指します。(設立準備中)
- 慶大GLab
代表 牧 英之
https://sites.google.com/keio.jp/glab/
http://www.az.appi.keio.ac.jp/maki/
ノーベル賞を受賞した「グラフェン」という最先端のナノカーボン材料を用いて、半導体のようにチップ上に集積可能な赤外光源など、世界初のナノカーボン光デバイスの社会実装を進めています。世界初のグラフェン光デバイスで安心・安全・健康なデジタル社会を実現するため、ナノカーボンデバイスの量産技術を基に、赤外分析、センシング、情報通信、素材などの広い分野で、革新的グラフェンデバイスを世界最速で社会実装することを目指しています。会社設立に向けて、慶大・プロジェクト名「慶大GLab」で活動しております。(設立準備中)
- フェルメクテス株式会社
代表取締役 大橋 由明
納豆菌タンパク質の実用化に取り組む国内唯一の企業として、世界が今抱えている食糧生産や環境問題の解決を目指すべく、納豆菌タンパク質の実用化に取り組んでいます。納豆菌特有の「圧倒的な生産効率」と「長い食経験」をもとに環境負荷の少ない効率的な食糧生産の実現と、新タンパク質食材である「kin-pun 納豆菌粉」の開発・普及を進めています。
- 株式会社Auxilart
代表取締役CEO 金 俊佑
Auxilartは数理モデルを用いたデジタルシミュレーションにより、医薬品製造プロセスにおけるコスト削減を実現するサービスを提供しています。これまで、医薬品の製造現場では、最適な製造プロセスを見つけるために、何千、何万もの実験を繰り返す必要がありました。同社はAIモデルが必要とするデータ量のわずか1%程度から高精度なシミュレーションモデルを構築し、必要な実験数を大幅に削減することが可能です。この技術によって、誰もが革新的な医薬品をより早く・安価に享受できる世界を目指します。
- Upmind株式会社
代表取締役 箕浦 慶
心身のケア(予防・未病)は、個人だけでなく政府・企業含め、重大な社会課題です。忙しい日常の中で心に余白を持つことの習慣化を促進しています。60万以上ダウンロードされているマインドフルネスアプリ「Upmind」の開発・運営(東京大学滝沢龍研究室とも共同研究)を軸に、今年度からは、法人向けの従業員の健康増進プログラムも展開予定です。全ての人が、”心に余白を持って幸せに生きることのできる社会”の実現を目指していきます。
- AI Mage Inc.
代表取締役CEO 張 鑫
日本の文化を代表するアニメ業界は、過酷な労働環境や人材不足に直面しており、抜本的な改革が求められています。AI Mageは、より良質なアニメ制作を実現するため、制作現場と緊密に連携し、最先端のAI技術を活用した最適なソリューションを提供します。日本発ならではの強みを最大限に生かし、世界の生成AI分野でリーディングカンパニーを目指してまいります。
- nook株式会社
代表取締役CEO 熊澤 龍生
z世代を中心にファッション業界で存在感を増す二次流通での購買。しかし、拡大の鍵を握るECでは、有名ブランドの服など一部のものしか取引がされにくいのが現状です。nookが開発する古着発見アプリReListは、日本中の中古服との、パーソナライズされたSNSライクな出会いを生み出しています。独自AIシステムが、曖昧なニーズと中古服をマッチングすることで、検索では難しかった安く買える理想の洋服との出会いを起こします。同社はAIに関する研究開発力と中古衣服領域での事業経験から、産業を垂直に改革し、自由でサステナブルなアパレル二次流通を牽引します。
- One Genomics Inc.
Co-Founder CEO Diana Luan
昨年初めてゲノム編集治療薬Casgevyが海外で承認され、今後ますます医療だけでなく食品、環境の領域でも技術の応用が期待されています。同社のコア技術である「セイフガードgRNA」は、様々なゲノム編集の応用ニーズに合わせた最適化を実現します。すでに米国にて登記されており、UC Barkley SkyDeckも修了して現在は国内外の製薬企業や、試薬メーカー等と協議を進めています。ゲノム編集の可能性を拡張する新しいイノベーションによって社会に貢献します。
技術シーズの社会実装を支援、国内初、大学横断・Non-Equity型最大規模の起業支援プログラム
※2021年の第5回目より、東京大学に加え、筑波大学、東京医科歯科大学、東京工業大学の参画を発表し、国内初の4大学共催起業支援プログラムへと進化しました。2022年4月には神戸大学、名古屋大学、一橋大学、北海道大学の4大学参画により、 8大学へ拡大。更に2023年3月、九州大学、慶應義塾大学、立命館大学、立命館アジア太平洋大学、早稲田大学が参画いたしました。
過去採択企業の資金調達成功率は約90%以上、大手企業との協業も拡大
また、関連大学の起業家教育プログラムとの連携により、全採択数のうち再応募からの採択は20~25%を占めており、アカデミアからの起業をより後押しする、エコシステム構築を目指しています。
新たに三菱商事、阪急阪神ホールディングスが参画し総勢24社へ。渋谷区、東京都との連携協定も。
また、2023年9月に渋谷区、東京都とスタートアップ支援を目的とした協定を締結いたしました。採択企業のPoCなどの共同支援を強化するとともに、大学関連スタートアップの支援機会の拡大を連携して進めてまいります。
第9回「1stRound」採択企業
- Star Signal Solutions(スターシグナル・ソリューションズ)株式会社
代表 岩城陽大
https://aerospacebiz.jaxa.jp/en/venture/star_signal_solution/
通信、天気予報、位置情報サービスなどの生活インフラの宇宙依存が進む中、宇宙での交通事故発生リスクが深刻化しており、その経済損失額は自然災害250個分(約25兆円)以上ともされています。Star Signal Solutions㈱は、宇宙ゴミや人工衛星などの観測・軌道解析を行い、宇宙での衝突事故回避ナビを提供することで「地上の暮らしと宇宙の安全を守る」JAXA認定ベンチャー企業です。(設立準備中)
- BlueWX(ブルーウェザー)株式会社
代表取締役 宮本佳明
乱気流は、航空業界において重傷を伴う事故の主要因で、安全性及び経済性に大きく影響を与えています。我々は、世界初の深層学習を用いた乱気流予測モデルを構築し、現在までに既存モデルを大幅に超える予測精度を実現しました。大手航空会社での実証実験により、高い評価を得たことから、高精度な乱気流予測を全世界の航空会社に提供することを目指すとともに、将来的に他業種においても気象リスクを最小限に抑えながら業務を遂行できる環境を提供したいと考えています。
- クレイ・テクノロジーズ株式会社
代表取締役 CEO 中田智文 / 代表取締役 COO/CTO 山下徳正
Qlayはマーケティングやリサーチ担当者向けの、生成AIモデルを活用した消費者リサーチツールです。商品企画やマーケティング業務において、オンデマンドで口コミサイト、SNSや自社データベースから消費者の声を自動収集、LLM(大規模言語モデル)を活用し消費者インサイトを抽出、アウトプットをダッシュボードに一括で可視化します。
- 株式会社DigitalArchi
代表取締役 松岡康友
https://www.digital-archi.com/
プラスチックを材料とする建築用大型3Dプリンタを開発、コンクリート型枠の域を超えた超多機能モジュール建材を低コストで製造し、現場作業を効率化する新工法を生み出しました。廃棄プラスチックのマテリアルリサイクルで資源循環を実現し、建設業のデジタル化と生産性向上を目指し、社会課題解決に挑みます。
- Planet Savers株式会社
代表取締役CEO 池上京
ゼオライトを用いた大気中からの二酸化炭素直接回収技術(Direct Air Capture: 以下DAC)を開発。2050年のCO2排出量ネットゼロ達成に向けて求められるDACにおいて、高効率のCO2吸着材とDAC装置を組み合わせ、実用化可能なレベル(100$/t以下でCO2を回収)のコストで実現。気候変動解決のフロンティアランナーを目指します。
- 株式会社MiRESSO
代表取締役CEO 中道勝
量子科学技術研究開発機構(QST)の認定を受けた核融合スタートアップ。核融合炉の運転には、ベリリウム(Be)が大量に必要になるところ、当社は低温精製技術により、圧倒的な低コスト・省エネでのベリリウム精製を実現しています。これにより、核融合の社会実装を目指すとともに、その他高温処理が必要な鉱物・素材の精製へと技術を発展的に展開して、経済安全保障の観点からも鉱物資源の安定確保に貢献する企業となることを目指します。
- Mesenkia Therapeutics
CEO Johan Lund
https://mesenkiatherapeutics.com/
難治性脳腫瘍として知られる神経 膠芽腫の治療標的分子として受容体型タンパク質HVEMに対する抗体を作製しマウスでの腫瘍抑制効果を確認。抗体のヒト化を完了、血中濃度の維持のためヒトIgGのFcを付けたものを作製した。サルでのPK試験などを完了し2年後の臨床試験開始を目指します。(設立準備中)
- 株式会社Scimit
代表取締役 CEO 石坂雄平
「AIをドライブし、音声コミュニケーションを革新する」というミッションを掲げ、AI音声変換ソフトウェアを開発・提供しています。音声の再現力が高い最新AIの活用や、音声合成サービスにより、誰でもなりたい声を表現できる時代を目指すとともに、身の回りのどこからでも声優などの各人の「推し声」が聞ける世界を構築していきます。
技術シーズの社会実装を支援、国内初、大学横断・Non-Equity型最大規模の起業支援プログラム
※ 2021年の第5回目より、東京大学に加え、筑波大学、東京医科歯科大学、東京工業大学の参画を発表し、国内初の4大学共催起業支援プログラムへと進化しました。2022年4月には神戸大学、名古屋大学、一橋大学、北海道大学の4大学参画により、 8大学へ拡大。更に2023年3月15日、九州大学、慶應義塾大学、立命館大学、立命館アジア太平洋大学、早稲田大学が参画いたしました。
過去採択企業の資金調達成功率は約90%以上、大手企業との協業も拡大
また、関連大学の起業家教育プログラムとの連携により、全採択数のうち再応募からの採択は20~25%を占めており、アカデミアからの起業をより後押しする、エコシステム構築を目指しています。
第8回「1stRound」採択企業
- 株式会社2DC
代表取締役 増田祐一
省スペース、安全、かつ広範囲なワイヤレス充電システム2D-Chargerを開発。様々なロボットやモビリティが共用可能な充電システムを規格化し、社会を支える新たな充電インフラの構築を目指します。
- 株式会社Visban
CEO 桒田良輔
ソフトウェアベースのメッシュネットワークコントローラを搭載したガラス基盤型ミニBase-Stationを開発。低コスト、かつ高信頼性ミリ波ネットワークデバイスの提供により6G通信を実現します。
- 株式会社OPERe
代表取締役 / CEO 澤田優香
患者のスマートフォンにて外来や入院における患者説明を行うコミュニケーションツール「ポケさぽ」を元看護師である現場の視点で開発。動画やメッセージを活用し患者説明を半自動化することで、現場の効率化推進と患者の満足度向上を目指します。
- 株式会社エンドファイト
CEO 風岡俊希
当社で扱う微生物『エンドファイト』は、すべての植物種に共生が可能で、植物を健康にし、病害や高温などのストレスに強くすると共に、花芽を誘導し美味しい実を付けるという前例の無い効果を提供。これら技術を通じて、通常では生育不可能な環境でも、高レベルな農業生産を可能とするサスティナブルな農業を実現し、農業にイノベーションを起こします。
- Anylom
CEO 萩原嘉廣
医師自らプレートをデザイン可能なソフトウェアの提供により、5日以内の短納期のカスタムメイド型骨折用プレートの納品を実現。 骨に解剖学的骨折用プレートがフィットしないアンメットニーズの根本的な解決を目指します。
- ProPlace
CEO 長沼大樹
脚本をAIで解析、プロダクト・プレイスメント(アニメ・映画などの作中に実在する商品などを露出する広告手法)可能なアイテムの抽出を行うことで、ブランドと作品の双方にとって最適な広告枠創出を実現。ストーリーから注目されるシーンを定量評価することで広告効果の最大化を目指します。
- Parakeet株式会社
代表取締役/CEO 中村泰貴
最先端のAI 音声変換技術を用いて、生まれながらにして変えられない (身体的制約) 個人の声色を自由にカスタマイズできるソフトウェアを開発。リアルタイムでの音声変換を実現することで、オンラインライブ・メタバースの音声ニーズに対応。
- 株式会社メタクロシス
代表取締役 新井康平
衣服の型紙を自動生成して3Dモデルを作ることで、3Dモデル作成のコストを大幅に削減。衣服のシルエットや質感を忠実に再現する新たなバーチャル試着サービスの提供により、全く新しい衣服の購買体験の実現を目指します。
過去採択企業の資金調達成功率は約90%、オープンイノベーションの事例を多数創出するアカデミア連携コンソーシアム型エコシステム
関連大学の起業家教育プログラムとの連携により、全採択数の中での再応募からの採択は20~25%を占めており、アカデミアからの起業をより後押しする、エコシステム構築を目指しています。
新たに三井金属株式会社が参画。EIR(客員起業家)を活用し大学内技術シーズからの起業支援も
また東大IPCは、2022年8月、経産省が実施する「客員起業家(EIR)の活用に係る実証事業」の実証事業者として採択されました。EIRとは起業増加とオープンイノベーション促進を両立するための仕組みです。新規事業創出を目指す事業会社などに、東大IPCが起業家予備軍の個人を紹介し、客員起業家(EIR)として参画することで、新たな事業の開発を目指します。 優れた大学の技術シーズの起業機会を多角的に支援、最大化することを目指して参ります。
第7回「1stRound」採択企業について
- 株式会社FerroptoCure
代表取締役CEO 大槻 雄士
世界初「フェロトーシス(細胞死)誘導性」抗がん剤を独自開発、高い「抗腫瘍効果」と「安全性」を両立し、かつ低コストでの提供を可能とすることで、アンメットメディカルニーズの解決を目指します。本採択期間では、資金調達の達成や治験準備を行います。
- 株式会社Premo
代表取締役Founder CEO 辻 秀典
チップ間通信を東大発の独自の無線化技術により、【基板レス】【超小型】【低価格】のチップサイズコンピュータを実現し、チップからIoT/DXにイノベーションをもたらします。デバイス開発側の論理ではなく、利用者側のデバイスに対する要求にこたえる形で、本採択期間では各種PoCを通じて具現化を進めます。
- issin株式会社
代表取締役社長 程 涛(Cheng Tao)
popInを創業し、世界初シーリングライト型プロジェクターを開発した程氏による新たなプロダクト。お風呂上がりに、乗るだけで体重管理できるスマートバスマットを開発。本採択期間中に、量産体制を構築し、正式販売開始予定です。
- キッズウィークエンド株式会社
代表取締役兼CEO 三浦 里江
https://www.kidsweekend.jp/portal
教育にテクノロジーを活用し、パーソナライズされた教育を届ける日本最大級のオンライン教育プラットフォームを展開。子どもと社会を繋いだ探究教育の提供や、教育を活用した企業のマーケティングを支援。本採択期間中に、企業や地方自治体との連携強化、大学との共同研究を通じたビジネスモデル特許取得を目指します。
- Letara株式会社
CEO/Co-Founder Landon Kamps COO/Co-Founder 平井 翔大
https://www.letara.space/ja/about
プラスチックを燃料とすることで、高推進・安全・安価な小型人工衛星用推進技術を提供。2024年宇宙実証機会の獲得を目指し、実証用デモ機の開発及び、開発拠点整備を展開しています。
- 株式会社ブリングアウト
代表取締役社長 中野 慧
https://www.bringout.biz/about
AIを活用して商談を見える化、分析し、アナログ作業の工数を削減と、「非認知能力」を再現可能なナレッジにする営業DXの実現を目指しています。既に大企業での導入実績も拡大中、本採択期間では、自然言語処理における大学との連携推進及び、顧客への販売・カスタマーサクセス機能の拡充を目指します。
- 株式会社ウェーブレット
代表取締役 髙橋明久
大学発の小型震源を用いた環境モニタリング技術の体系化・システム化を行って、振動観測を用いた実用レベルのモニタリングの提供を目指します。本技術は、地盤変動・社会活動・地熱発電・CCS等の環境モニタリングに貢献します。本採択期間では、2022年実施予定の共同研究実現に向けた、システム構築を強化します。
- 株式会社アークス
代表取締役兼CEO 棚瀬将康
生殖補助医療現場で活動する胚培養士の人材不足を解消すべく、臨床現場における作業の自動化アタッチメント・シャーレの開発によって、コスト低減と高い成功率の両立を目指しています。本採択期間ではプロトタイプの検証と製品化に向けた体制構築を目指します。
過去採択企業の資金調達成功率は約90%、オープンイノベーションの事例を多数創出
「1stRound」採択後は、ハンズオン支援および各社最大1,000万円の活動資金の提供に加え、東大IPCによる採択先と大手企業との協業機会の創出や、東大IPCが運営するオープンイノベーション推進1号ファンド(以後、AOI1号ファンド)をはじめとするベンチャーキャピタル等による資金調達を支援し、採択先の事業の垂直立ち上げを目指します。
新たに株式会社STNet、ダイキン工業株式会社、三井物産株式会社が参画。総勢18社へ。
第6回「1stRound」採択企業について
- reverSASP Therapeutics株式会社
代表取締役 二見崇史/大堀誠
URL:www.reversasp.com
細胞老化分野の大家である中西研究室の各種成果を基にしたバイオテックベンチャー。
老化バイオロジー解明に基づく各種疾患治療薬創製を通じ、健康寿命の延伸への貢献を目指します。本採択期間中では、研究・事業開発を推進するチーム組成及び資金調達を目指します。
- 株式会社Ememe
代表 深原エマ
https://ememe.ai/
3Dモーションキャプチャー機能を備えたNFTマーケットサービスを開発。スマホでユーザー独自のモーションを作成し、NFT化します。また、作成したモーションはチャットでのスタンプ利用の他、メタバース空間ではアバターのエモートとして利用できます。代表自身もアバター経営者として活動。本採択期間中に、実用最小限の機能開発とともに初期ユーザー獲得までを目指します。
- 株式会社Octa Robotics
代表取締役 鍋嶌厚太
https://www.octa8.jp/
ロボットと建物設備の連携を可能にするインターフェースサービスを開発。
自律移動ロボットの生産性は、フロア間・エリア間の移動ができると飛躍的に向上します。標準プロトコルに準拠したエレベーター連携を皮切りに、防火扉・セキュリティゲート連携に機能拡大し、建物全体をロボットの移動範囲にすることを目指します。
- 株式会社LearnWiz
代表取締役 中條麟太郎
https://one.learnwiz.jp/
東京大学4年生の代表が、教育工学を研究する吉田塁研究室における活動からのスピンオフとして創業。参加者の主体性を高めながら、参加者間の意見交換・集約を促すWebサービス「LearnWiz One」を開発。授業やイベントにおける活用のみならず、企業におけるブレストや会議の場面でも活用が広がっている。
2022年1月に世界最大の EdTech コンペ「GESAwards」R&D部門世界大会で優勝。2022年3月には、代表が本取り組みの成果から東京大学総長大賞を受賞。本採択期間にて、機能開発に加えて教育機関および企業への展開を広げます。
- G-Bank Technologies OÜ/株式会社GIG-A
CEO Raul Alikivi(ラウル アリキヴィ)
https://www.gig-a.jp/
元エストニア経済通信省局次長を務め日本とエストニアをつなぐ連続起業家であるCEOが手がける、バンキングを中心とした外国人が日本で働く際の課題を包括的に解決するサービス「GIG-A」を開発。
「GIG-A」は個別に存在する外国人向けサービスを包括的に代行し、銀行口座開設から生活サービスに至るまで日本版WeChatのように様々な機関と連携し、パーソナルコントロールセンターとしてペイン解決を目指します。採択中は、プロダクト開発と、銀行や規制当局との調整対応に注力します。
- 株式会社ヘッジホッグ・メドテック
CEO 川田裕美
https://h-medtech.com/
臨床・厚生労働省・IT企業を経験した医師である代表が、治療用アプリの開発を目指し2021年10月に創業。片頭痛の治療として一般的な薬物療法に加え、医療機器アプリを介した認知行動療法(日常行動のパターンを含めた認知を改善する治療法)を組み合わせることで、更なる治療効果の向上を目指します。頭痛領域ではアプリの開発及び薬事承認の取得に向けた準備を進めており、また他の疾患領域等への展開も視野に入れ、チームを引き続き強化していきます。
- 株式会社エルシオ
代表取締役 李蕣里
https://www.elcyo.com/
±6度以上の超広範な度数可変範囲と直径30mm以上の大口径を実現したフレネル型液晶レンズをベースとした世界初のアイウェア開発。軽量・安価・省エネ駆動である度数可変レンズでのオートフォーカス(視力矯正機能)実現によって、外的環境によらず幅広い実装が可能になり、老眼、強度近視、弱視等の視力問題解決を目指します。まずは液晶レンズ駆動ユニットの小型化実現によるプロトタイプ完成に注力します。
- 株式会社Meshbase
代表 岡﨑健斗
https://warrantup.com/
保険/保証のデジタル販売プラットフォーム「WarrantUp」を開発
保険領域のDX化は、中小のみならず大手も手が届いていない分野です。販売から運用までの全プロセスをカバーすることで、事業者にとっては手軽に保険/保証の販売体制を構築できるだけでなく、導入後の運用コストを抑えることが可能となります。採択期間中は、対応可能な保険を拡充し、導入先を増やすことに注力します。
過去採択企業の資金調達成功率は約90%、オープンイノベーションの事例を多数創出
また、「1stRound」は創業と最初の資金調達を支援すると同時に、AOIファンドの出資企業、およびコーポレートパートナーとの協業関係の創出にも力を入れてきました。
既に採択先と各企業との資本業務提携など、オープンイノベーションの事例が10社以上生まれております。また2020年からは採択先に対する東大IPCによる投資も開始し、既にBionicM株式会社、株式会社アーバンエックステクノロジーズ、HarvestX株式会社、ソナス株式会社、ヒラソル・エナジー株式会社、株式会社Yanekaraに対する投資を実行済みです。
新たに6社の各業界リーディングカンパニー及び山内ファミリーが参画。総勢17社へ。
第5回「1stRound」採択企業について
- 株式会社EVAセラピューティクス
代表取締役 尾﨑拡
「腸換気法」を用いた、新規医療機器開発
https://evatherapeutics.site/<代表よりコメント>
EVAセラピューティクスは、「臓器の再生により新たな医療を作る」ことをビジョンとする東京医科歯科大学発ベンチャーであり、武部貴則教授の革新性の高い「腸換気法」を用いて、新規医療機器開発を試みる企業です。酸素化したパーフルオロカーボン(PFC)を肛門経由で投与することにより、呼吸不全患者の低酸素状態を改善し、増悪によるECMO・人工呼吸器への移行を抑制します。挿管を伴う治療は合併症のリスクに加え、多大な医療資源を要する事から、腸呼換気法による新たなモダリティは医療資源及び患者のQOLに多大な貢献をもたらすと考えられています。PFCは人工血液、手術材料、造影剤等に既に応用されており、実用化の可能性が高い技術と期待しています。
- Logomix, Inc.
代表取締役 相澤康則
合成生物学技術で、バイオエコノミーの実現
https://logomixgenomics.com/<代表よりコメント>
Logomixは、合成生物学技術で、バイオエコノミーの実現を目指しております。独自のゲノム大規模構築エンジニアリングプラットフォームを通じて、機能性化合物の物質生産に活用される微生物のゲノムだけではなく、ヒトゲノムをはじめとする構造が複雑なゲノムを効率よく設計改変し、産業価値のある細胞システムの構築を推進することで、パートナー企業とともに産業的価値や社会的価値を創造します。現在、主に3つの分野(医療・ヘルスケア、バイオマテリアル・化学・エネルギー、農業・養殖・環境)で事業を展開しております。
- VesicA Intelligence, Inc.(予定)
代表 池田篤史
膀胱内視鏡検査における、AI技術とIT技術を活用した検査支援システムの開発
https://www.vesica.jp<代表よりコメント>
VesicA Intelligenceは、膀胱がんの診療に欠かせない膀胱内視鏡検査において、AI技術とIT技術を活用した検査支援システムの開発を行っています。
膀胱がんは、術後2年間で約50%の症例で膀胱内再発をきたすと報告されています。これには、尿を貯める嚢腔(ふくろ)である膀胱内を効率よく観察し、位置関係を正確に記録することが容易ではないため、膀胱内視鏡検査や手術において、医師の病変に対する視認能力に不可避的にバラつきが生じることが影響しています。
私たちは、検査を行う医師をテクノロジーで支援し、すべての膀胱がん患者さんの治療成績向上を目指します。
- 株式会社LeadX
代表取締役 前田将太
製造現場のリードタイムを短縮し、設計と製造のフィードバックループを加速する、SaaS開発
https://www.leadx.co.jp/<代表よりコメント>
これまで世界を代表する製品を輩出してきた日本の製造業界は、今や人材不足や技術承継困難、国際的な競争力の低下など、幾多もの根深い課題を抱えています。私たちは産学官のあらゆるリソースを集結させ、この途轍もなく大きな課題の解決に挑戦します。
製造現場とソフトウェアの融和によりリードタイムを極限まで短縮し、設計と製造のフィードバックループを加速することで、高付加価値な製品が世界中で創出され続ける製造業界を実現します。
- CrestecBio株式会社(予定)
代表 丸島愛樹
重症虚血性脳卒中で生じる脳虚血再灌流障害を克服できる新たな治療薬CTB211の開発
https://crestecbio.hp.peraichi.com<代表よりコメント>
重症虚血性脳卒中では標準治療を行っても十分な治療効果を得られず、多くの患者が後遺症に苦しんでいます。CrestecBioのミッションは、重症虚血性脳卒中で生じる脳虚血再灌流障害を克服できる新たな治療薬CTB211を患者さんへ届けて転帰を改善することです。そのために、画期的新薬であるCTB211を脳梗塞病巣に効果的に送達させる技術の確立、非臨床試験から臨床試験の実施、重症虚血性脳卒中に対する新たな治療の提供を目指します。CrestecBioは脳神経外科医の臨床経験と基礎研究の成果を融合して、最先端の科学と技術の進歩を、患者さんや社会への価値に変えていきます。CrestecBioが切り開く未来は、疾病からの組織保護と機能再生のイノベーションにより、健康寿命延伸が実現する世界です。
- 株式会社Robofull
代表取締役CEO 山本大
製造工程毎に標準化された産業用ロボットシステムの開発・販売
https://www.robofull.com/<代表よりコメント>
Robofullは工場で使用される産業用ロボットシステムの販売を通じて、人手不足に苦しむ中小製造業のペイン解消を目指します。
現在の産業用ロボットシステム業界では、顧客毎にシステムがオーダーメイドで設計・製造され、「費用対効果の分かりにくさ」、「費用の高さ」につながっています。Robofullは、顧客に最適なロボットシステムの価格・仕様を数秒で出力する自動設計ツールに加えて、顧客工程毎に標準化したロボットシステムの設計・販売を通じて、こうした課題の解消を行ってまいります。東大IPCとの連携のもと、人手がなくてもよりよい社会の実現のために事業化を推進してまいります。
- DataLabs株式会社
代表取締役 田尻大介
三次元点群データの自動モデリングから熱や気流等の各種シミレーションまでをSaaSで提供。計測サービスを含め一気通貫で展開
https://datalabs.jp/<代表よりコメント>
DataLabsのミッションは「デジタルツインの社会実装」を通じて、最適化された社会の実現に資することです。近年、建築土木や都市開発、交通、エネルギーインフラ等の業界において、生産性向上の手段の1つとしてデジタルツインの構築・活用が急務となっています。一方、その利活用には高額なツールと高い専門性が求められ、社会実装のハードルとなっております。この課題解決として、DataLabsは三次元計測にも対応しつつ、点群データの自動三次元モデリング(BIM/CIM化等)及び、熱流体や気流、構造解析等の各種シミュレーション(CAE解析)機能をSaaSで展開。UI/UXを充実させ、デジタルツイン実現のハードルを極限まで低減します。これにより、生産性向上をはじめ、業界横断的に対応が迫られる多様な社会課題の解決に寄与いたします。
- エミウム株式会社
代表取締役兼CEO 稲田 雅彦
歯科医療・歯科技工プラットフォームの開発
https://www.emium.co.jp/<代表よりコメント>
当社は「歯科医療・歯科技工のインフラになる」という企業ビジョンを掲げ、歯科医療・技工技術、デジタル製造技術、AI技術を融合した事業の開発と提供を手掛けるデンタルテックスタートアップです。創業以来、大学病院との研究連携や歯科医院・歯科技工所など国内外の関係各所へのヒアリングを通じて、非効率性・高コスト体質などの業界課題を特定し、それらをデジタルソリューションで解決すべく、歯科医療・歯科技工のためのデンタルプラットフォームの構築を進めています。今回の東大IPCさんの1stRoundの支援を最大限に活用し、事業化を推進して参ります。
- 株式会社アモス光機
代表者 王立輝
大口径液体レンズの開発、製造、販売事業
https://www.amos-koki.com/<代表よりコメント>
アモス光機は大口径液体レンズの開発、製造、販売事業を行います。液体レンズは従来の機械的な移動が必要な固体レンズと比較すると、速度、大きさ、コスト、機能性などで優位性をもつ革新的な光学デバイスです。液体レンズの大口径化を実用化し、産業用マシンビジョン、車載デイスプレイ、プロジェクター、ヘットマウントディスプレイ、眼科用医療機器などに応用、これまでのレンズの限界を超えていきます。
過去採択企業の資金調達成功率は約90%、国内大手企業との協業機会を創出
また、「東大IPC 1st Round」は創業と最初の資金調達を支援すると同時に、AOIファンドの出資企業(※2)およびコーポレートパートナー(※3)との協業関係の創出にも力を入れてきました。既に採択先と各企業との資本業務提携など、オープンイノベーションの事例が10社以上生まれております。また2020年からは採択先に対する東大IPCによる投資も開始し、既にBionicM株式会社、株式会社アーバンエックステクノロジーズ、HarvestX株式会社等に対する投資を実行済みです。
新たに株式会社安川電機、ピー・シー・エー株式会社のコーポレートパートナー参加が決定
第4回「東大IPC 1st Round」採択企業について
- 株式会社Yanekara
代表取締役 松藤圭亮
商用電気自動車をエネルギーストレージ化する充放電器とクラウドの開発。
https://yanekara.jp/<代表よりコメント>
Yanekaraは「自然エネルギー100%の日本を創る」というミッションを掲げています。このために電気自動車を太陽光で充電し、それらを群制御することで電力系統の安定化に必要な調整力を創出できる充放電システムを開発しています。電気自動車が拠点や地域内の太陽光発電で走るだけでなく、駐車中に遊休資産となっている車載バッテリーから調整力を生み出すことができれば、エネルギーの脱炭素化と地域内自給、さらには高い災害レジリエンスを実現することができます。1st Roundの支援を活用させていただくことで、プロダクトを完成させEV利用企業への提供実績を作り、Yanekaraシステムの社会実装に繋げます。
- 株式会社Citadel AI
代表取締役 小林裕宜
AIを可視化し、AI固有の脆弱性・説明責任リスクからお客様を守る事業
https://citadel.co.jp<代表よりコメント>
AIは賞味期限がある生鮮食料品のようなものです。出来上がった瞬間から社内外の環境変化のリスクに晒され、品質劣化が始まります。AI固有の脆弱性を狙ったアタックも存在します。さらにAIの説明責任・コンプライアンスの観点から、学習データに潜むバイアスにも常に注意が必要です。弊社では元米国Google BrainのAIインフラ構築責任者が開発をリード。AIの思考過程を可視化の上、お客様のAIの品質・信頼性を確保する「AI監視ツール」を提供します。オンライン・バッチ環境、学習・運用フェーズのいずれにも対応、様々なAIシステムへの適用が可能です。「24時間いつでも頼れるAIをあなたに」これが我々の目指す事業ビジョンです。
- 株式会社EVERSTEEL
代表取締役 田島圭二郎
画像解析を用いた鉄スクラップ自動解析システムの開発。
https://eversteel.co.jp/<代表よりコメント>
EVERSTEELのミッションは、鉄スクラップの自動解析システムにより鉄鋼材リサイクルを促進し、世界のCO2排出量を削減することです。鉄鋼材生産によるCO2排出量は、世界の製造業全体の25%と最も多く、排出量を4分の1へ低減できるリサイクルの促進が望まれます。しかし、リサイクル過程での不純物混入による鉄鋼材の機能低下で、多大なコストが発生しています。鉄鋼メーカーでは、不純物混入制御を、現場作業員の目視で行っており、品質と作業効率に限界があります。私たちは、自動解析システムを実用化することで、高効率・高精度な不純物混入制御を実現します。そして、世界の基盤材料である鉄鋼材のリサイクルを促進することで、世界規模でのSDGs達成への寄与を果たします。
- 株式会社LucasLand
代表 望月昭典(暫定)
バイオ産業にDXをもたらす簡便微量分析法の開発。
www.lucasland.jp<代表よりコメント>
創薬、食品科学、環境安全、感染症検査、科学捜査等のバイオ産業において微量分析はとても重要ですが、一般的な微量分析法(X線、NMR、質量分析等)は分析装置の大きさやコストが問題であり、簡便微量分析法である表面増強ラマン分光法は生体試料への適合性の問題がありました。我々のミッションは、この難問を解決した東大発の新素材「多孔性炭素ナノワイヤ」( https://www.s.u-tokyo.ac.jp/ja/press/2020/7032/ )を用いて、バイオ産業全般のデジタルトランスフォーメーション(DX)に資する微量分析プラットフォームを創造することです。今回の東大IPCの支援を最大限に活用し、事業化を推進します。
- ANICLE株式会社(予定)
代表 高橋昂平
獣医業界のDXを進める遠隔ペットケアサービス事業
https://anicleofficial.studio.site<代表よりコメント>
ANICLEは、すべてのペットが最適なヘルスケアを受けられる社会の実現を目指します。今の獣医業界には、様々なハードルにより飼い主が動物病院に行くタイミングが遅れ、救えたはずの命が失われているという深刻な課題があります。ANICLEはITを活用し、遠隔獣医療サービス(トリアージ、オンライン相談・診療、往診など)を提供することで、獣医療へのアクセスの改善を実現します。さらに家庭と動物病院を繋ぎ、シームレスなヘルスケアをペットが受けられるように、獣医業界のDXを進めます。
過去採択企業の資金調達成功率は約90%、国内大手企業との協業機会を創出
また、「東大IPC 1st Round」は会社立ち上げと最初の資金調達を支援すると同時に、大手企業と有望な東大関連ベンチャーの協業関係の創出にも力を入れています。既に採択先とパートナー企業の資本業務提携など、パートナー企業と採択先企業のアライアンスが多数実現しております。2020年からは採択先に対する東大IPCによる投資も開始し、既にBionicM株式会社等に対する投資を実行済みです。
新たに物流業界をけん引するヤマトホールディングス株式会社のパートナー参加が決定
第3回「1stRound」採択企業について
- 株式会社JIYU Laboratories
代表者 高野 泰朋
所在地 東京都港区
事業内容 学術論文の自動要約サービスによる情報収集の効率化
URL https://www.paper-digest.com/<代表よりコメント>
私たちは、学術論文を人工知能の技術で要約して、非英語圏研究者の研究効率を劇的に向上させることを目指しています。一流の学術論文は英語で書かれています。それを、何時間もかけて読んだ末に、結局自分にとって関係ない内容であることが判明することがよくあります。そこで、私たちは、論文要約サービス「Paper Digest(ペーパー・ダイジェスト)」を開発することで、文章全体を読むことなく、その内容がユーザーにとって有益であるかを判断できるようにします。メンバー2人は、いずれも大学の研究者です。ユーザー目線での開発に強みがあります。今回の東大IPCの御支援を最大限に活用させて頂き、より多くの研究者たちにお役立ちできるように、事業化を推進してまいります。
- セレイドセラピューティクス株式会社
代表者 荒川 信行
所在地 東京都文京区
事業内容 造血幹細胞の体外増幅技術を用いた医療への応用
URL https://www.celaidtx.com<代表よりコメント>
新たな治療法として、幹細胞を用いた医療への応用が近年注目されています。中でも血液の源である造血幹細胞は、白血病などのがんを始めとする難治性の血液疾患や遺伝子疾患など、様々な疾患の治療に有益であるとされています。今の臨床現場では、造血幹細胞を体外で増幅することは難しく、性質の良さを最大限に利用できていません。私たちは、造血幹細胞の体外増幅技術を活用することで、これまでにない医療への応用方法を提案し、新たな治療法を開発することを目指します。今回の東大IPCからのご支援の下、スピーディーに事業化を進め、一日でも早くより豊かな社会作りに貢献したいと思います。
- 株式会社SoftRoid
代表者 野﨑 大幹
所在地 東京都文京区
事業内容 建築現場を巡回しデータ収集するソフトロボットおよびアプリの開発
URL https://www.softroid.jp<代表よりコメント>
私たちは、建設業界の労働生産性向上を目指しています。製造現場ではセンサを配置し「データ収集→可視化→分析→改善」により生産性向上を図りますが、建築現場では人手による断片的な写真撮影と目視による進捗管理が行われており、データ収集・活用が進んでいません。この課題を解決するために、私たちは建築現場で想定される不整地や階段を走破可能なソフトロボットと現場の可視化・分析アプリケーションを開発しました。センサを搭載したロボットが建築現場を自動巡回することで「データ収集→可視化→分析→改善」というサイクルを可能にし、建築現場の労働生産性向上を推進します。
- ARAV株式会社
代表者 白久 レイエス樹
所在地 東京都文京区
事業内容 重機の遠隔・自動化により現場をアップデート
URL http://arav.jp/<代表よりコメント>
建設業界は、市場規模が60兆円と大きいにもかかわらず、求人に対して16.6%しか働き手が集まらず、55歳以上が約35%かつ29歳以下が約11%と他業界よりも高齢化が進んでおり、深刻な人手不足が続いております。ARAVは既存の建設機械に後付で先進機能を追加することで抜本的に上記の課題を解消します。
- HarvestX株式会社
代表者 市川 友貴
所在地 東京都文京区
事業内容 植物工場における自動受粉・収穫ロボットシステムの開発
URL https://harvestx.jp<代表よりコメント>
私たちのミッションは、農作物の完全自動栽培で人類の食糧問題を解決することです。現在、レタスやバジルといった葉物野菜の植物工場は多いですが、果菜類の植物工場はほとんど存在しません。その理由として一般的に受粉に用いられるミツバチの飼育が困難なこと、工場内における受粉手段が欠如しているといった課題があることが挙げられます。
また、受粉に関しては現状ほとんどの作物がミツバチによる虫媒受粉に頼っているため、代替手段となる技術開発が求められています。
私たちはロボットによる受粉・収穫技術を確立し、果菜類の植物工場、完全自動栽培を実現することを目指しています。東大IPCの支援を受け、今後イチゴだけでなく多種多様な作物への応用など、より加速して研究開発及び事業化を推進して参ります。
- 株式会社ヤモリ
代表者 藤澤 正太郎
所在地 東京都渋谷区
事業内容 収益不動産を最適化するクラウド不動産経営管理ソフト
URL https://www.yamori.co.jp/<代表よりコメント>
ヤモリは「不動産の民主化」をミッションに、所有不動産の収支を可視化して、管理業務を効率化するクラウドサービスを提供しています。既に個人と法人の不動産オーナーと管理会社にご利用頂いており、約100億円の不動産資産を管理しています。
不動産投資に関する情報は閉ざされているため、不動産の所有は一部の人に偏っています。これが空き家や建物の老朽化、低属性の方の入居拒否増加といった社会課題の根幹にあります。我々はデジタル技術を活用し、しっかりと賃貸経営ができる不動産オーナーを増やすことで、賃貸市場を活性化させ、透明性ある不動産市場を実現していきます。
- ORLIB株式会社
代表者 佐藤 正春
所在地 東京都文京区
事業内容 二次電池および関連製品の企画、製造、販売、輸出入と知的財産許諾事業
URL https://satoh88.wixsite.com/orlib<代表よりコメント>
私たちは多電子反応を利用した高エネルギーで、エコ、安全、低コストの新世代二次電池の実用化を目指しています。最初に、軽量・高エネルギーの特徴を生かしてドローン向け電池に取り組み、現在のドローンが抱える飛行時間が短いという課題への解決策を提示します。これにより、新型電池としての実績を確保して他の広範な用途への電池の展開の基礎とします。これまでよりも大きなエネルギーを手軽に、安価に貯蔵し、必要に応じて取り出すことができるため、持続的で豊かな社会の実現に貢献することができます。
採択1年以内の会社設立割合は100%、資金調達成功率は90%
「東大IPC 1st Round」は会社立ち上げと最初の資金調達を支援すると同時に、大手企業と有望な東大関連ベンチャーの協業関係の創出にも力を入れております。既にヒラソルエナジー株式会社と芙蓉総合リース株式会社の資本業務提携、エリー株式会社に対する三井住友海上キャピタル株式会社の投資など、パートナー企業と採択先企業のアライアンスが2件実現しております。
この度、東大IPCは1st Round第2回目の支援先を決定したことと、トヨタ自動車株式会社および日本生命保険相互会社を新規パートナー企業として迎えることをお知らせ致します。
第2回「1stRound」採択企業について
- Pale Blue
代表者 : 浅川 純
所在地 : 千葉県柏市
事業内容 : 小型衛星用水推進機の開発・販売
URL : https://pale-blue.co.jp/<代表よりコメント>
小型衛星の更なる市場拡大には、宇宙空間で能動的に小型衛星を動かすための推進機が必要不可欠になります。しかし、大型衛星用の推進機は高圧ガスや有毒物を推進剤として用いており、体積・重量・コストの観点から小型衛星に適用することは困難でした。Pale Blueは、東京大学で研究を進めてきた、安全無毒で取扱い性・入手性の良い水を推進剤とした小型推進機の技術を社会に実装することで、小型衛星の市場を拡大させつつ、持続的な宇宙開発を実現します。本プログラムの支援を受け、法人設立及び事業展開を行っていきます。
- 株式会社ファンファーレ
代表者 : 代表取締役 近藤志人
所在地 : 東京都港区虎ノ門4丁目3−1 城山トラストタワー4階
事業内容 : 廃棄物業界の省力化・効率化
URL : https://www.fanfare-kk.com<代表よりコメント>
私たちのミッションは労働人口不足で立ち行かなくなる廃棄物業界の省力化・効率化です。まずは産業廃棄物回収の省力化に取り組んでおり、弊社サービスを利用すると配車計画作成にかかる時間が1/100以下になります。全国の産廃業者とリレーションが既にあること、業務自動化の高い技術力があることを強みとしております。東大IPCからのご支援を受けて、強靭な社会インフラの構築をよりスピードアップできればと思っております。
- UrbanX Technologies
代表者 : 前田紘弥
所在地 : 東京都目黒区
事業内容 : 道路点検等、都市インフラのリアルタイムデジタルツインの構築
URL : https://www.urbanx-tech.com<代表者よりコメント>
私たちは、スマートフォンやドライブレコーダなど広く普及している簡易デバイスのみを用いて、都市空間のリアルタイムデジタルツインを構築することを目指しています。特に、現在注力しているのは、車載スマートフォンからリアルタイムにポットホールなどの損傷箇所を検出できる道路点検システムMyCityReport for road managers (https://www.mycityreport.jp)で、My City Reportをコアに、様々な道路管理業務の日常をイノベートしていきます。今回のご支援を受け、まずは道路からスタートして、都市空間全体のデジタルツイン構築へと研究開発・事業化を推進して参ります。
- 株式会社スマートシティ技術研究所
代表者 : 薛 凱
所在地 : 東京都足立区
事業内容 : 社会インフラの点検・診断支援
URL : https://www.smc-tech.com/<代表者よりコメント>
社会インフラの効率的な維持管理にむけて,道路の状態をスマートフォン1台で簡単に定量評価する技術を開発しました.当初から世界展開を目指して,簡易で安価な評価手法と,高精度で高信頼な定量評価との両立をコンセプトに開発してきた技術です.独自の車両振動解析技術とAI画像処理技術を駆使することで、桁違いに高価な専用測定車両に劣らない点検精度を実現しました.国内外における運用で高く評価された実績を持ちます.基礎理論と最先端技術を武器に、ゆくゆくは道路の分野のみならず、様々なインフラ維持管理の分野で、弊社の技術を広めていきたいと存じます。
- 株式会社Liquid Mine
代表者 : 代表取締役 近藤 幹也
所在地 : 東京都港区
事業内容 : リキッドバイオプシーを用いた次世代の白血病遺伝子検査
URL : http://www.liquidmine.co.jp<代表者よりコメント>
血液内科医として白血病診療に従事している中で、様々な問題を抱える従来の白血病検査法では、時に本当に最適な治療方針を立てることができない現状があり、何とかその問題を解決したいという想いでLiquid Mineを設立しました。独自の遺伝子解析手法と液体生検(リキッドバイオプシー)を組み合わせた、負担の少ない血液からの高精度な検査を開発し、今なお不知の病として知られる白血病に苦しむ患者さんに最適な治療環境を提供することを目指しています。
- 株式会社 Magic Shields
代表者 : 代表取締役 下村 明司
所在地 : 静岡県浜松市東区有玉南町1867−1
事業内容 : 高齢者の骨折を防ぐ、転倒時だけ柔らかくなるマット・床の開発
URL : https://magicshields.webnode.jp/<代表者よりコメント>
高齢者の転倒による骨折は、国内で毎年100万人発生しており、本人と家族の苦しみに加え、医療費・介護費増大の原因ともなっています。このような社会課題を解決するため、私たちは「歩くときは硬く、転んだときだけ柔らかくなるマットと床『coroyawa(ころやわ)』を開発しています。今回の東大IPCの御支援を元に、いち早く骨折の不安を抱える皆さまにcoroyawa(ころやわ)を届け、骨折から高齢者とその家族を守り、最期まで尊厳を持って生きられる社会を実現していきます!
インキュベーションプログラム「東大IPC 1st Round」を開始
2019 年4月からは、各業界のリーディングカンパニーと共同で、支援対象・支援規模を大幅に拡大したコンソーシアム型のインキュベーションプログラム「東大IPC 1st Round」を開始し、初代コーポレート・パートナーとして、合計6社(JR東日本スタートアップ株式会社、芙蓉総合リース株式会社、三井住友海上火災保険株式会社、三井不動産株式会社、三菱重工業株式会社、株式会社竹中工務店など)が参加しています。
第1回「1stRound」採択企業について
- Mantra
代表者 : 石渡 祥之佑
所在地 : 東京都文京区
事業内容 : マンガの自動翻訳エンジン・多言語配信プラットフォームの開発
URL : https://mntr.jp https://pf.mntr.jp/<代表よりコメント>
私たちのミッションは世界中のマンガ作家とファンを正しくつなぐことです。 従来のマンガ翻訳のプロセスは煩雑・高コストであるため、海外では海賊版が氾濫しています。私たちは画像認識と自然言語処理の技術を組み合わせたマンガ専用の翻訳エンジンでこの課題を解決し、すべての作品が即時的かつ低コストで読者に届く世界を実現します。
- 株式会社iMed Technologies
代表者 : 代表取締役CEO 河野 健一
所在地 : 東京都渋谷区
事業内容 : 脳梗塞・くも膜下出血に対する手術支援AI
URL : https://imed-tech.co.jp/<代表よりコメント>
脳神経外科医師として16年間勤務してきましたが、医療現場で脳血管内手術の課題を感じ、『世界に安全な手術を届ける』という理念を掲げ、2019年4月に共同創業者の金子とiMed Technologiesを設立し起業しました。現在、くも膜下出血や脳梗塞に対する脳血管内治療のリアルタイム手術支援AIを開発中です。東大IPCの御支援を最大限に活用させて頂き、事業化を推進してまいります。
- 株式会社イライザ
代表者 : 代表取締役CEO 曽根岡 侑也
所在地 : 東京都文京区
事業内容 : AIによる需要予測と自然言語処理
URL : https://elyza.ai/<代表よりコメント>
機械学習やDeep Learningという言葉は2010年代において広く普及しましたが、まだまだ技術・社会実装の両面において、多くの未解決問題が残っており、実用化という面では普及が進んでいないのが現状です。ELYZAでは、① 現在パラダイムシフトが起きつつある自然言語処理(NLP)、② 小売・製造業におけるAI活用(リテールテック)の2つに焦点を当てて、社会全体を巻き込むイノベーションを起こすべく研究開発を行なっています。今回のご支援を受け、今まで開発を行ってきたリテールテックにおける需要予測AIのサービス化を進めて参ります。
- Jmees
代表者 : 松崎 博貴
所在地 : 千葉県柏市
事業内容 : 内視鏡手術支援AI
URL : https://jmees.ml/<代表よりコメント>
私たちは外科手術を安全に行うために、術者をAIによって支援するシステムを開発しています。従来の手術では、熟練医が持つ優れた解剖構造の認識力、手術工程の計画力、術中の判断力全てがブラックボックスであるため、それらを習得するには多くの経験を積む必要があり習得が困難でした。私たちが開発するAI手術支援システムでは、手術映像をリアルタイムに解析し術者の認識力を支援することで、より安全に手術が行えるようにします。
- スマイルロボティクス株式会社
代表者 : 代表取締役 小倉 崇
所在地 : 東京都文京区
事業内容 : 外食産業向けロボット
URL : https://www.smilerobotics.com/<代表よりコメント>
飲食店でテーブルを自動で片付けるロボットを作っています。人手不足で困っている外食産業にロボット技術で少しでも貢献出来ればと思っています。現在3人のメンバーは全員が元Google (SCHAFT)でロボット開発をしてきた仲間です。不可能に挑戦し夢を現実に変えていくチャレンジは今も続いています。
- エリー株式会社
代表者 : 代表取締役 梶栗 隆弘
所在地 : 東京都中野区
事業内容 : シルク(蚕)フードの開発・販売
URL : https://www.ellieinc.co.jp/<代表よりコメント>
弊社は蚕を原料とした食品『シルクフード』の開発を進めるスタートアップです。昆虫食は資源利用効率が良く、地球環境に優しい次世代の食品です。弊社は、それに加えて、蚕の持つ機能性/栄養成分に着目して研究を進めています。世界では徐々に昆虫食市場が拡大し始めていますが、将来、その先陣を切る企業になるべく、当プログラムを通じて邁進して参ります。